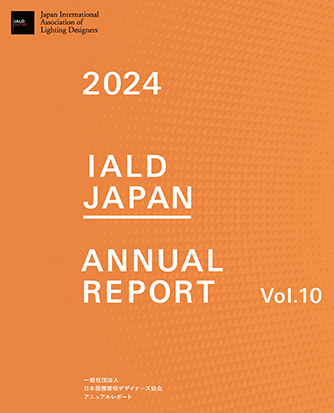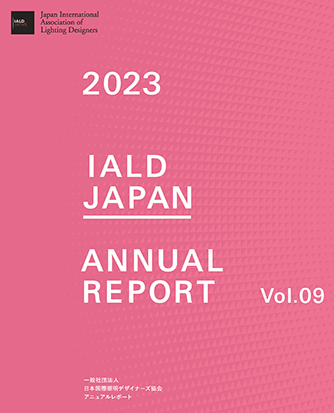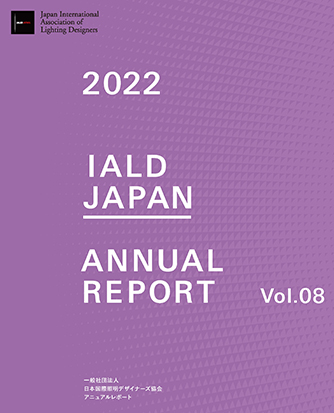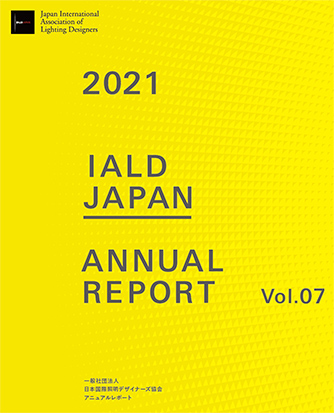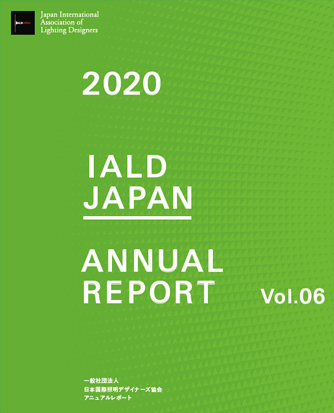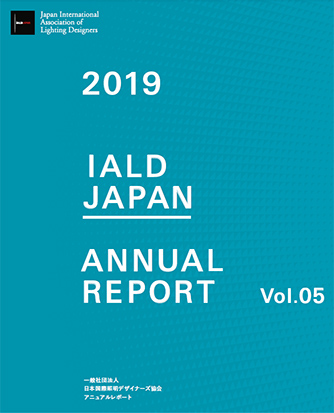Activity
イベント レポート

第63~65回コミュニケーションバーInaBarレポート
InaBarは『照明デザイナー同士のコミュニケーションをとる場を作りましょう。』という発案から始まったIALDJ会員限定のコミュニケーションバーです。 リアル感を大切に長年続いてきました。今後も Face to Faceで集うことを基本方針として開催して参りますので、まだ参加されたことのない方もマイグラス持参で是非一度のぞいてみてください。「ここだけ」の話を聞けるかも・・ご来店をお待ちしております。 出張InaBar、出前InaBar、昼下がりのInaBarなども開催いたします。お楽しみに! 参加資格:IALD-J会員 場所 :主に IALD Japan事務所 開催日 :月初めの火曜日(休み月あり、事前にメールにてお知らせ) 2024.12.03 第63回 『光のギフト』 開催場所 :IALD Japan事務所 来店者全員が「光のギフト」の画像や実際の「光」を持ち寄って語り合いましょう。という内容でした。 光を皆さんと共有しようとインゴマウラー社の「My New Flame」を持ち込んだ小山さん。 プルンプルンのゼリーキャンドルを紹介した山下さん。 […]
Read More
照明デザイナーズ・フェス 2024
2024年11月8日(金)の正午から夜まで、東京デザインセンター5Fのクラフテックギャラリーにて、「照明デザイナーズ・フェス2024」が開催されました。本イベントは、日本商環境デザイン協会、日本インテリアプランナー協会 東京、日本空間デザイン協会の共催によるもので、照明の未来をテーマに語り合う場となりました。出入り自由の3部構成で行われ、多くの照明業界関係者が集まり、大いに盛り上がりました。 第1部は、「Enlighten Asia 2023」からの継続イベント「照明トレンドオンステージ」でした。6つのテーマを掲げ、参加メーカー様のプレゼンテーションを通じて、最新の照明技術やデザインのトレンドを紹介し、深く探る内容となりました。 第2部では、2つの特別セミナーが開催されました。1つ目は、地震の多い日本におけるペンダント照明の補強について、様々な地震動を想定した振り子実験を用いて解説が行われました。2つ目は、個人事務所を営む方々に向けて、新たに施行されたフリーランス法について解説する内容でした。いずれも日常に直結するテーマで、参加者にとって興味深い講演となったことでしょう。 第3部では、「人間と空間照明の明日」をテーマに、参加者同士の親睦を深める懇親会が行われました。冷えたハイネケンのボトルビールを片手に、照明の未来について活発な意見交換が行われ、和やかな雰囲気の中で交流が深まりました。 このイベントは、今回を含め全3回の開催が予定されています。照明メーカーと照明デザイナーをつなぎ、照明の未来について語り合える貴重な場として、これからも発展していくことを期待しています。 【第1部:照明トレンドオンステージ】 テーマ1「センサーは光のコンシェルジュ?」 登壇メーカー:コイズミ照明株式会社、株式会社遠藤照明、神田通信機株式会社 このテーマでは新たな照明のトリガーとなる技術や未来像が語られました。コイズミ照明、遠藤照明では自社オフィス内で積極的にセンサーを導入し、人の動きや気象情報、外部画像をトリガーにして明制御や空調制御にその情報を反映させています。神田通信機からはIDカードなどと連携した制御呼出しや、人の睡眠状況を反映した制御呼出しの採用が始まっているという最新情報が紹介されました。これらの技術の向上には異業種間の情報共有が欠かせないという事が今回のテーマにおける最大のポイントであると感じました。 テーマ2「暗いのも素敵です」 登壇メーカー:スワン電器株式会社、株式会社ビートソニック LEDの発光効率が劇的に進化し、意図した以上の照度を確保することが容易になった昨今、明るさと暗さの適度なバランスについて考える必要があるのではないか、というテーマでスワン電器とビートソニックの2社に語っていただきました。 両社とも調光技術で明るさを落とすという視点ではなく、必要最低限のあかりをつくるという視点で器具開発を行っており、空間に適度な明るさを持たせつつ存在感のあるフィラメントタイプのLEDランプが紹介されました。 またLEDランプで課題となる調光についても、よりスムーズで白熱電球に近い調光調色の実現に成功しており、フィラメントタイプのLEDランプの未来を感じる発表となりました。 テーマ3「見せるライン照明は好きですか?」 登壇メーカー:株式会社ネオ・ストラクト、株式会社Luci 様々なラインモジュール照明が登場していますが、その活躍の場はどのように広がっているのでしょうか?建築照明デザインの視点以外にもインテリアデザインや建築的な視点から見た「見せるライン照明」の可能性や疑問点をネオ・ストラクト、ルーチの2社に語っていただきました。 […]
Read More
第60~62回コミュニケーションバーInaBarレポート
InaBarは『照明デザイナー同士のコミュニケーションをとる場を作りましょう。』という発案から始まったIALDJ会員限定のコミュニケーションバーです。 リアル感を大切に長年続いてきました。今後も Face to Faceで集うことを基本方針として開催して参りますので、まだ参加されたことのない方もマイグラス持参で是非一度のぞいてみてください。「ここだけ」の話を聞けるかも・・ご来店をお待ちしております。 出張InaBar、出前InaBar、昼下がりのInaBarなども開催いたします。お楽しみに! 参加資格:IALD-J会員 場所 :主に IALD Japan事務所 開催日 :月初めの火曜日(休み月あり、事前にメールにてお知らせ) 2024.09.03 第60回 『イタリア流の生き方に学ぶ』 スピーカー:コルベッラ・マルコ氏、ジオ・クロッティ氏 開催場所 :IALD Japan事務局 今回は、2名のイタリア人男性をゲストに迎えました。 イタリア人の多くは日本人とはだいぶ違って、物事を進めるために綿密に計画を立てることをしません。という既成概念で始まりました。 案の定、マルコさんは遅れてご来店。しかし二人は仕事があるとのことで昔の日本人のように、InaBar閉店後、会社に戻っていきました。日本人よりも日本人らしいイタリア人2名・・・『物事を進めるために綿密に計画を立てません。』納得のInaBarでした。 提供されたワインはイタリアピエモンテ州のワインでした。 […]
Read More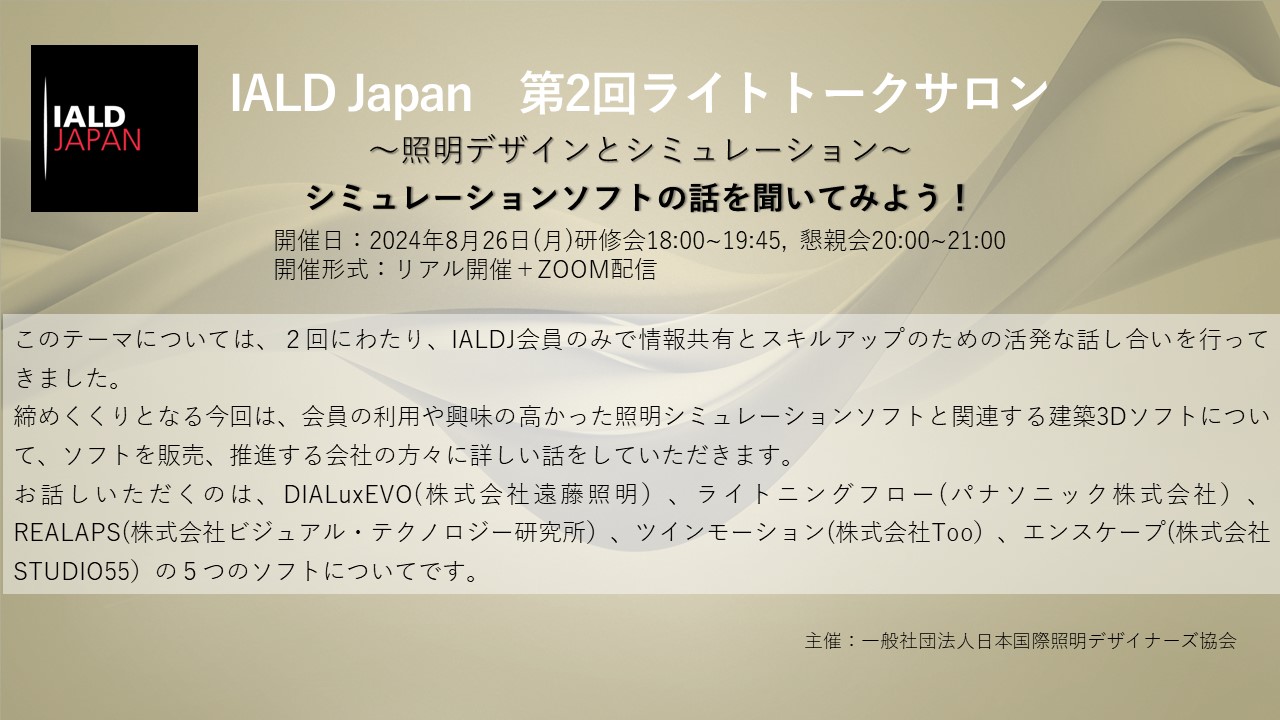
第2回ライトトークサロン「照明デザインとシミュレーション~シミュレーションソフトの話を聞いてみよう!~」
IALD Japan主催の第2回ライトトークサロンが2024年8月26日に開催されました。 今回は「シミュレーションソフトの話を聞いてみよう!」というテーマで、DIALux evo・REALAPS・Twinmotion・Enscape・Lightning Flowといった照明シミュレーションソフトやそれに関連するソフトの開発・販売等に携わる企業の方々にご講演いただきました。 照明シミュレーションソフトDIALux evoについてご説明いただいたのは、ソフトを開発したDIAL社のパートナー企業の株式会社遠藤照明さんです。「DIALux evoは、無料ソフトで、イメージとしてはパソコンで建築の3D模型を作り、照明器具の配光データを入れて光の効果を検証するという感じで使用するものです。そして最大のメリットはDIAL社と契約している照明器具メーカーなら、世界中のどのメーカーの照明器具・配光データでも入れて検証できることです」と、実際に照明器具を入れて作成された3Dモデルを紹介されました。屋外からの視点やフロアごと部屋ごとの視点など、いろいろと視点を変えて光の効果を検証できるのが特徴で、このソフトを活用すれば光の計画内容がビジュアルでわかるため、施主とプランナーが照明に対する要望や不安要素を共有しやすくなります。 TwinmotionとEnscapeはCADやBIM等のソフトで使用するプラグインでTwinmotionについて、販売代理店の株式会社Tooさんは「スピード感を重視していて、いろんなツールに対応しているのが特徴です」とし、「最近トレンドの人感センサーといった動きのあるシーンで一番表現力があります」というお話もされました。開発元であるEpicのアカウントを作り、制作したシーンをクラウドに保存すれば、施主もWebブラウザ上でそのシーンを体験できるのは大きな魅力です。 Enscapeについて、ソフトの代理店の株式会社STUDIO55さんは「IESデータの活用が可能で、レンダリングのスピードが速いのが特徴です」と解説されました。一方で「マテリアルの反射の表現は苦手かな」というお声も。ただ、レンダリングソフトの中では珍しく照明ビューの設定ができるので、「空間のどこが明るいかを視覚的につかむためのツールとして活用してもらえれば」とのことでした。 株式会社ビジュアル・テクノロジー研究所さんは、提供されているREALAPSについて「照明のシミュレーション値を輝度・色度分布に変換して、実際の光の見え方と比較することができるソフトです。照明デザインで最初に考慮するのは照度ですが、光の見え方を検証するためには輝度を把握する必要があります」と解説。さらに周辺の色によって「順応」という現象が起き、見え方は変化するため、「それも考慮して明るさを推定しなければいけないのです」と述べられました。シミュレーションしたりVRで見たりした光は何となくそれを正しいと感じてしまうため、輝度・色度分布等で本当の見え方を確認するという方法は新鮮で、光の見え方の再考にもつながりました。 最後のパナソニック株式会社さんは、Lightning Flowについて「BIMや3DCADのソフトで作成した建築・照明データを瞬時に取り込み、光の効果を確認できるソフトです」と解説し、最大の特徴としてスピードと精度を挙げられました。それは「従来の照明シミュレーションの課題とされていた光の再現の計算時間を大幅に短縮し、かつ国際照明委員会が推奨する精度基準に準拠した高精度なものです」と語られました。そのスピード感を示す検証データによると、一般的によく使用されるソフトでは45秒かかる光の計算が1秒で終わるということ。光環境の確認が速くできれば、その分照明の位置変更等の多くの試行が可能になるので、自分たちの理想とする建築空間により近づけるのではと期待が持てました。 そして、最近手がけられているスタジアム等の光演出といったDMXサポートにも触れ、Lightning FlowDMX対応の照明器具をつないで、その実演をしていただき、第2回ライトトークサロンの講演は終了しました。 講演終了後には会場の方とZOOMでの視聴者から続々と質問が寄せられ、企業の方のご回答にみなさん熱心に聞き入っていました。 【開催日】2024年8月26日 【会場】MY Shokudo Hall […]
Read More
第57回~59回コミュニケーションバーInaBarレポート
InaBarは『照明デザイナー同士のコミュニケーションをとる場を作りましょう。』という発案から始まったIALDJ会員限定のコミュニケーションバーです。 リアル感を大切に10年間続いてきました。今後も Face to Faceで集うことを基本方針として開催して参りますので、まだ参加されたことのない方もマイグラス持参で是非一度のぞいてみてください。「ここだけ」の話を聞けるかも・・五反田本店でお待ちしております。 今後は出張InaBar、出前InaBar、昼下がりのInaBarなどの開催も考えております。お楽しみに! 参加資格:IALD-J会員 場所 :主に IALD-J事務所 開催日 :月初めの火曜日(休み月あり、事前にメールにてお知らせ) 2024.04.02 第57回 『皆さん何してる?』 スピーカー:武石正宣 開催場所 :ICE都市環境照明研究所 InaBarの在り方を模索している中で、今までのように話題を決めて開店するには、話題提供者になる会員が及び腰になり、なかなか見つかりません。 そこで、InaBarの基本に戻り、会員同士のコミュニケーションに重点を置き『皆さん何してる?』という軽い感じで、出前InaBarで開店しました。その記念すべき第1回出前Inabarはタケちゃんこと、武石 […]
Read More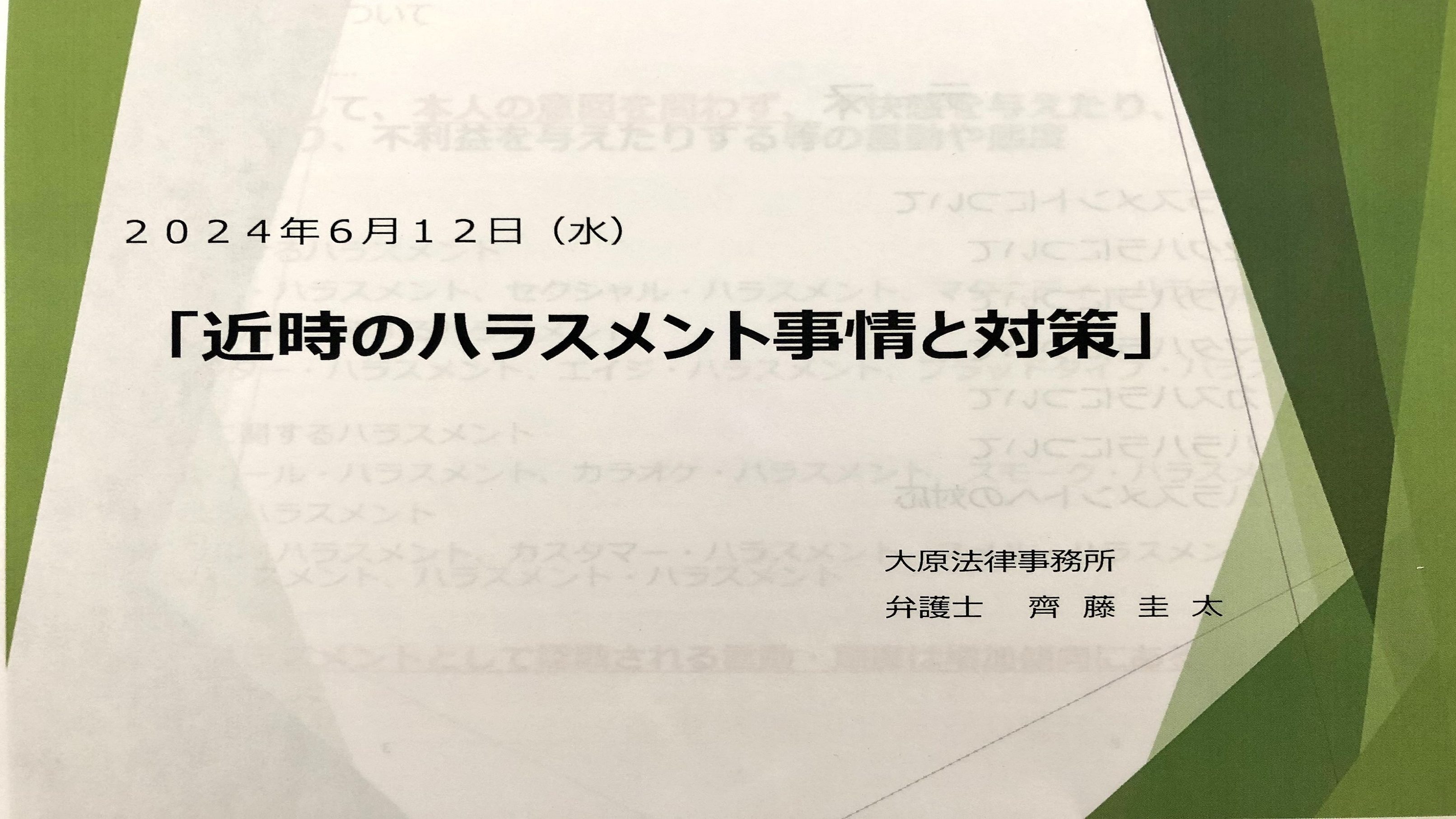
第1回 コンプライアンス研修会
IALD Japan主催のコンプライアンス研修が、大井町きゅりあんで2024年6月12日に開催されました。 講師には弁護士の齊藤圭太先生をお招きして、「近時のハラスメント事情と対策」というテーマでお話しいただきました。 齊藤弁護士はまず、「一般的にハラスメントとは行為者の意図を問わず、他人に不快感や不利益を与えたり、尊厳を傷つけたりする言動や態度」と説明し、ハラスメントを行った人が「そんなつもりはなかった」というのは通じませんと話されました。 そして指摘されたのは、近時ハラスメントとして認識される言動や態度は増加傾向にあることです。ジャンルごとにパワハラやセクハラ、エイジハラスメント、ジェンダーハラスメント等を簡単にご紹介、「本日はパワハラとセクハラを中心にお話しします」と前置きされました。 最初に、セクハラについて。 厚生労働省によるセクハラの定義は、「職場において行われ、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が不利益等を受けること」と説明し、勤務時間外の飲み会での言動も、その飲み会が職務の延長と考えられればセクハラに当たりうることや、性別に関係なく行為者・被害者になりうること等を話されました。 そして、セクハラに当たるかの判断基準について「受け手の主観を重視しつつ一定の客観性が必要で、平均的な男性または女性労働者の感じ方を基準にする」と解説し、食事などへの執拗な誘いや、パソコンで卑猥な画像を見るといった行為はセクハラになり得ますと述べられました。 続いて、パワハラについてです。 パワハラとは「職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為」で、その「優位性」について、上司から部下への行為だけでなく、同僚間や部下から上司に対する行為もパワハラになり得るとして、 「業務の適正な範囲」に関して、単純ミスを繰り返す病院職員に対する厳しい指導がパワハラになるか問われた裁判で、「生命をあずかる医療現場でのその行為は当然になすべき業務上の指示の範囲内のものでパワハラに当たらない」とした裁判所の判断を事例として挙げられました。 その後、妊娠・出産等を理由に解雇等の不利益な取り扱いをするマタニティハラスメント、カスタマーハラスメント、ハラスメント・ハラスメントについても軽く触れられました。 カスタマーハラスメントの解説では、顧客からクレーム等を受けた場合、その要求の根拠や事実関係、こちらに落ち度がなかったかを確認することが大事であること。 カスハラか否かは、要求を実現する手段・態様が、今の社会の考え方を基準にして許されるかどうかで判断されるなどと解説されました。 ハラスメント・ハラスメントとは、「業務指示など正当な行為に対してハラスメントと主張する行為」と説明し、ハラ・ハラを放置すると上司が部下に注意しにくくなるため、仕事の質が下がったり職場の雰囲気が悪くなったりしますと指摘もありました。 そして、「ハラスメントに対して会社は何をすべきか」という話に移り、 […]
Read More
石井幹子名誉理事の旭日中綬章叙勲記念祝賀パーティー
日本国際照明デザイナーズ協会 初代代表理事の石井幹子さん(株式会社石井幹子デザイン事務所代表取締役)が長年にわたる照明デザイン業界の発展に尽力された功績により旭日中綬章を受章されました。これを祝して、日本国際照明デザイナーズ協会主催で「石井幹子氏の旭日中綬章 叙勲記念祝賀パーティ」が築地聖路加ガーデンタワー レストランLUKEにて催されました。 当日は、パーティ―のドレスコードである“光るもの”を出席者全員が身に着け、石井さんを囲んで照明業界の未来を語るカジュアルで和やかなパーティが開催されました。十人十色の“光るもの”を身に着けた参加者と主催者がダンスミュージックに合わせて楽しみ、笑顔と歓声に満ちた素晴らしい幕開けとなりました。 大きな拍手の中、イルミネーションベールをまとった石井さんが華やかに入場されました。発起人代表として近田玲子理事より、石井さんとの思い出話が語られました。 「ひとつだけ皆さんにお話したいのが、ある時、石井さんが、”デザインというのは静かな池の中に石をポンとなげるようなものよ。近くに投げた時は小さな波紋が早く寄せてくるけど、寄せてくる範囲が小さいのよ。でも遠くに石を投げると波紋が池の周囲全体にいきわたるでしょ。そうことがデザインではないかと私は思っているのよ“とお話いただいたことがありました。社会に対しても行き渡る、そういうことをあの時すでに考えていらっしゃったのだなと今思い出しております。今後も益々のご活躍を祈っております。」と挨拶がありました。 続いて、ご来賓である日建設計取締役会長 亀井 忠夫氏、三菱地所設計代表取締役副社長国府田道夫氏のご紹介、そして同じくご来賓の元駐イタリア大使、元国際交流基金理事長、東京国際映画祭チェアマンの安藤裕康氏よりご祝辞をいただきました。安藤氏には、「1978年日本のこれからの政策ビジョンの中で、照明デザイナーとして石井さんと初めてお会いし、その時から存在感があった。日本、そして海外で素晴らしい仕事を沢山され、世界における日本のプレゼンスを高めるために石井さんは大いに貢献されました。ソフトタッチで柔和でありながらも、あきらめないチャレンジ精神が素晴らしい方です。日本そして世界中を駆け巡り、照明デザインに尽力され日本が誇れる人になったことを強調したい。まだまだ上の賞がございます。これからも世界中で授賞していただきたいと思っています」とご挨拶いただきました。 さらに、株式会社I.C.O.N. 代表、フランス照明デザイナー協会(ACE)副会長 石井リーサ明理氏からのビデオメッセージが流されました。 そして、石井さんのお気に入りのシャンパンが日没と共に振る舞われると、会場ではパナソニック株式会社エレクトリックワークス社常務 ライティング事業部長 島岡国康氏のご発声で盛大に乾杯が行われ、生演奏とともに楽しい歓談のひとときが始まりました。 続いて、石井さんが光り輝く純白のレースのドレスに身を包んで再びステージに登場されました。この素晴らしいドレスはIALDメンバーの山下裕子氏が手がけたデザインで、会場からは喝采と盛大な拍手が沸き起こりました。 参加者からの質問コーナーとして、昨年ENLIGHTEN […]
Read More
Chase the Dark 2024
IALD Japanの息抜き企画、Chase the dark 2024を 今年も3月21日(木)に行いました。 テーマはずばり”Upcycling”. ゴミになってしまう缶や瓶を再利用して、そこにティーキャンドルを灯したりします。 今年も本気で工作しながら、普段はゴミとして簡単に捨ててしまう素材達にあらためて向き合って、様々に考えを巡らせることのできる楽しい時間でした。 普段の仕事で忙しく過ぎていく時間の中で、童心に帰って工作を楽しむ時間と、純粋に光に向き合うことができるChaase the darkに今後もみなさん、どんどんご参加ください。 […]
Read More
第55回~56回コミュニケーションバーInaBarレポート
InaBarは『照明デザイナー同士のコミュニケーションをとる場を作りましょう。』という発案から始まったIALDJ会員限定のコミュニケーションバーです。 リアル感を大切に10年間続いてきました。今後も Face to Faceで集うことを基本方針として開催して参りますので、まだ参加されたことのない方もマイグラス持参で是非一度のぞいてみてください。「ここだけ」の話を聞けるかも・・五反田本店でお待ちしております。 今後は出張InaBar、出前InaBar、昼下がりのInaBarなどの開催も考えております。お楽しみに! 参加資格:IALD-J会員 場所 :主に IALD-J事務所 開催日 :月初めの火曜日(休み月あり、事前にメールにてお知らせ) 2024.02.06 第55回『新宮晋さんに触発されて!−照明デザインと自然エネルギー』 スピーカー:野澤壽江さん 開催場所:IALD Japan事務所 話題提供は野澤壽江(のざわひさえ)さん。 話題は第54回の『Enlighten Asia […]
Read More